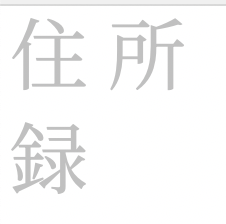こう、
こう、漫然と歩いているだけでも10分20分、3、40分。風が吹いて、さあと言う。
それは見事な空の穴で、見ていると、本当にそう見えてきた。白銀の月がこうこうと輝いているのだった。満月は昨日だったのだけど、その前後の方が、つよく輝いているように思える。手前に雲がうすく流れ、そのあいまあいまで円く穴が見える。いつの間にかもう12月だから空気が凍っているよう、冷たく澄んでいて。
さっきマッサージ屋さんであたたまった体がもう冷えようとしている、早くうちに着かないものか、そう思いながらも足取りはすでに寄り道を始めている。あたまのなかではさっきみたライブの音が流れていてそれも五月蝿かったものだから、あたりが静かでノイズの余韻、つーと何か音がじっさいにしているようで、どこか店にでも入らないと落ち着かない。
黒がいいよ! あの濃密な黒!
誰かが叫んだ。
いや私はもっとしゃばしゃばした黒がいいわ! 感覚のことで言い合うのは厭だけれどこれはビジネスだもの!
ビジネス的に考えてもあの黒の強さが断然いい!
いや違うわ、あのしゃばしゃば感がイマっぽいのよ、こう麻を浅く染めたような黒! どうにもこうにもフィットするようじゃない!
そんなこと言うあなたがしゃばしゃばしてるよ! しゃばしゃばしてるものに時代が変えられるのか! 新しいものをつくれるのか!
時代を変えるってそんなアーティストみたいなこと言わないで、これは仕事なのだから!
喧噪が慌ただしい。しかし内容がどうも、こう、聞く人のことを意識しながら言い合っているような雰囲気もする。
ここは地下にある飲み屋であって、飲み屋というかカフェと言った方が合っているのかもしれない、もっと気さくに立ち寄れて何となく酒を飲み、何となく本を読み、タバコを吸う。気のきいたジャズが轟音で流れている。しかし彼らが話しているその仕事、一体どんな仕事なのだろうか。本を読む目は全然進まず、彼らの言葉に気をほとんどとられている。同時に、自分の仕事のことさえ浮かんできている。これは、悪い気分ではないのだけど、仕事のことをとりあえず忘れてゆっくりしようと思ってここに来たのだから、そういう自分が力なく仕事に浸食されているようで、クサクサとしてきてしまう。そうして酒を進める。酒といっても弱いものだからビールばかり飲む。たまにハイボールも飲む。あとは甘い割ものであるので、酒飲みとは言えないだろう。けれど毎日、時には毎朝毎昼飲むのだから、軽く依存していると言ってもいいのだろう。どうしてなのか分らないが、人は依存してしまう。もたれ掛かってしまう。ちょうどいいものに。最初はいい、それから暫くはいい、けれどもたれていると段々、その角度が深くなっていって、いつか破調している、そうなった時にどうするのかは人によるが、こう、どーんと壊してしまってそれから考える人もいるだろうし、まあ大概は放っておけばなるようになるよと言ってなるようになるようにする人もいるだろうし、よし! 俺は何とかする! と言って何とかする人もいるだろう。何か、生活自体を変えるとかして。
生活とは何なのだよ! 僕らの日々に生活なんてあるのかよ!
あるわ! しょうがないけどベラボウにある!
僕の心を読んでこんなことを言うのだろうかこの2人は。
いや違うあなたは全部口に出しながら考えてる! それもこれも筒抜けに!
そうだったのか。これは酒のせい? それとも前からのクセなのだろうか。
いやワカらないがあなたの言葉は全て私らの心にクリアに入って来る! この店の店員の言葉よりも、このウルさいジャズよりも! 何だろうか、テレパシー?
ある人とよく、連絡をとる時、じゃあ何かあったらテレパシーしますね、と言い合っていた。言いながら日々、エスカレートしていくのは冗談の常であって、テレパシーか伝書鳩、手旗信号、あるいは、手鳩信号になった。手が鳩のように動き、それで何か信号をサインを送るのだろうか。
あのそれでまた、空隙をぬってああ、ああ、と言って、庭を見ている。ひたすら、あのぽっかり空いた空隙を見つめている。
それで淡々とまた手、鳩、信号を、送っている。手は鳩のフリをして、もぞもぞ動いている、たまに、足を胴にうずめ休憩したりする、芸が細かい。でもぐっとくるわけではない。鳩のああいう仕草は気持悪い、あと目のまわりのぶつぶつも気持悪い、という人がいる。まあ分らないでもないけれど、それはなんか神経質に気にし過ぎではないかな。
それで鳩のいた、森について考えている。あれは言葉でしかなくて、実際に行くと樹や石や草やもろもろが混沌としているのだった。しかしどうもあまりに行きたくて恋焦がれる。ああ、と思う。行く。
旅ばかりしていても仕方がない。ただ景色が変わり続けるだけ。前へ進んでいるかというとそうでもない。疲れる。でも生な時間が淡々と流れる。その時はつまらないようであっても、何か時間の感触が手に残る。でも、色々求めてもしようがない。
ある時そうして森に焦がれたが、遠くへ行く時間も余裕もなかったので、自宅の横にある林に立ち、時に撮影もし、少し森を感じては過ごしていた。森というのは言葉であって、ただのイメージでしかない。けれどそのイメージが私らの生をつくる。
頭の中にあるのはインドで見た沈黙の塔だった。あれは入ることは許されない、行者たちが過ごし死んでいく墓だったか。何だろう、風葬するのか?いや、鳥葬だったか。
森が滝であることもあった。あれも実際にあるのは、水が激しく上から下に落ちる様、どうどう流れ、しとしと落ちる。
道を行くと、ふぁと向うから自転車がやってくる、すれ違う、ふぁ、と風が吹く。
踏切がなっている、きんきんきんきん、それに合わせて何かぴいぴい鳴っている、踏切に鳥が棲んでいるのじゃなかろうか。あ、鳩。手、鳩。ちょっと待って、ダウンロードしている。踏切の向うにはアパートが見える。「FREEDOM」と建物の壁にある看板にある。
車掌が走って、鳥をいさめた。無線で何かハナシをしている。
………どうぞ、ああどうぞ……
そう言っている。そうして日々はいっとき物語のようになるがただ日々でもある。で歩く、たまに手をとりあい草むらに寝転がる。
踏切待ちのタクシーはUターンをし客を探しにいった、人らはまだ踏切があがるのを待っている。向う側にもいる。
歩く線は一本線でなみなみしている。
白い壁が続いている。白い廊下、白い部屋。歩いていくと、4つ目の部屋が、白い受付のようになっている。ちょうどカメラ屋の受付を白に塗り込めたよう。
受付に誰も立っていない、よく見ると右奥の隅、本棚とイスがあるところ、2人が抱き合って動かない。どちらも男とも女ともつかない。壁側のひとは髪が長く肩は丸く、女性かと思うが分らない、目を見開きこちらを見ている。前の人は背が低く髪が長い。何だか犬っぽい、赤茶の巻き髪をしている。彼らの輪郭線だけ白壁に強く映えている。
その光景をいつだって覚えている、むしろそれしか覚えていない。その日そこの壁面に沢山何か飾られていたことも朧げでしょうがない。どうして思い出せないか、数日前のことなのに、数年前のようにも思える。
日付が嘘のように進んでいる。ぼうと日々を過ごしてきたということなのか、忘れるほど濃密で色々あった日々なのか、何だかそれも分らない、ぼうとしている。居つづけたかった、そこらにしゃがみあぐらを組んで、けれどそれも悪目立ちしそうだから、よくない。
今思い出したがふたりの傍らには大きな樹があった。そこは新宿のあるビルの一角だったけれど、ツリーハウスというものもあるし、観用植物もいろいろだからさして不思議でもないが、大きな大きな樹が立っていた、根元しか見えない。そこに彼女はよりかかるようにしていて、手前にひとりがおおい被さっていたのだった。そうして彼女は何かを呟いた。かぶさる人にしか聞こえないように小声で「誰か来て見ているよ」「ねえ」「好き……」なんてどれでもないだろう。表情は無く、ただうろんとこちらを見ていた。
空が見えなくなるまで、ずっと見ていた。
少しして壁の先に目をやると、蛇のようなかたちで女が雑巾をかけている。腰を折りうつぶせて。しゅるしゅると手を動かす、顔はこちらを向いている。目鼻立ちがはっきりとした、明るい人。
それは中谷さんだった。彼女の祖母さんは、華道の先生をしている。著書も数冊ある。ある年代より上の人なら大体知っている。
中谷さんはよく奇異な行動をとる。そのたび「私の祖母は、●○なの」と言い訳をする。そうしてにまと笑う。その寄り目がちな笑顔が素直で愛嬌に満ちていて、いくらくだらないことをしても悪い気にならない。
彼女とは電車に乗っていて知り合った。夜、終電車に近い頃ぼくがウトウトとしていると隣の彼女が大きな包みを膝に乗せていた。ビニールで包まれた大きな鉢植えだった。枝葉が広がり、かなり大きい。だから電車の揺れるにつれゆさ、ゆさ、と揺れる。先っぽの方がビニールからはみ出ている。それがこう、段々と顔に近づいてきて、枝が鼻にあたる。あたるたび目が覚めるが酔いの常ですぐまたウトウトする。しばらく繰り返していくうち、それに気づいた彼女が、包みをなおし始めた。包むうち、枝といっしょに僕も包んでいる、鼻から、上、あたまの方、下、顎のほう、だんだんと包んでいく。その手つきはやさしい。包まれるうち、肩、腰のあたりが紐でくるまれる。次第に鉢植えと一緒になっていく。何とも言えぬ心地よさがあったが、はっと目ざめるとそれは終点で僕の家のある駅だったのでよし降りようと思った、何か包まれているが足は自由なので、共にくるまれていた鉢植えを抱え降りる。ああ重い。降りて立つと、ひとつ隣の出口から彼女が出てきて彼女も立ってこちらを向いている。それであの笑顔で、にまにまとしている。
彼女もいくらか酔っているのだろう、それかこの夜の空気に合わせふにゃふにゃしているのかもしれない、駅のベンチに腰かけ僕を包んだビニールを、かいがいしい様子で、ほどいてくれる。
人気のない、けれどホームらしいホーム。壁ぞいに長くつづく木のベンチ。休みの日には、昼間からビールを飲みながら談笑するおじさんの2人組がいたりし、なかなかに和やかなところだった。今は終電のひとつまえ、来るひとを待っているのだろう女性がひとり、少し離れたところに座っていた。ケイタイをいじっている。ホームの屋根は途中までしかなく、先は空。互いのホームはつながっておらず、一度出て、踏切を渡らないと向う側にはいけなかった。ある時から何故か、青いLEDのライトがつくようになった。宇宙的な光。
風が吹いている。ぬるりとした風が。
あるスイッチがある、上を推すと順回転、下を押すと逆回転する。何のスイッチだろうか。ベルトコンベア? ミキサー? そんなことを、つらつらと考えていた。
趣味は何ですか。
中谷が、ビニールをほどく間の沈黙もあれなので質問をした。趣味って何だろうか。たとえば映画を見るのは好きだけどそれは映画の中味を追っているのであって映画自体を見る時間を愛しているわけでもない。いや好きだけど趣味と言えるほど好きではない。それでアルタミラの壁画について思った、人が集落を作って、狩りをして帰って、洞窟の壁に絵があった方がいい、落ち着く、これが人間だ、それが趣味の起源ではないか。
いやそれはたぶん芸術であって趣味とは違うのです。趣味とはもっと何か依存するようなもの、精神安定剤のようなところもあるのでしょう。映画が趣味という人が会社にいて、その人はホラーしか見ない、血まみれの顔が出てくるやつしか見たくない。それを日々見ないと気がすまない。
というか聞かれて困るのなら無趣味、でいいのじゃないでしょうか。映画はよく途中から見ます。だから映画館に行っても、だいたい90分をこえる長さだとどこかで寝てしまう。ビールなど飲むから尚更眠くなる。だから一部がわからなくともまあいいかと、漫然と見る。それで面白いと畜生寝なきゃよかったと思う。でも寝ないで見通したって、どうせ忘れていきます。
そうですね。見たあとに街を歩くのは面白いです。頭の中で映画が再生されながら実際の景色も動く。
どこかで手順を誤ったらしい。中谷さんはやや本気にビニールと格闘しているが、どうも以前よりビニールに閉じ込められている感がする。
映画をはじめから見ると、何かあたまのなかでストーリーを再構築、つまりあたまのなかで筋道をきちん、きちんと作りながら、見ている。最初はこうで、こうなって、でこうなって、あなたを、それで抱きしめるのだな、それで別れるのだな、と追憶しながら見てしまいます。
わかります。でも、あなたって誰ですか、わたしのことではないでしょう。誰に話しているんですか。
*
そとはだんだん、日暮れていくね
タローとジョーは、夜道を駆けた。疾駆した。
疾駆しながらタローは、何故「疾」にはやまいだれ、が付いているのか、疑問に思った。疑問は、新しい景色を生んだ。景色はこう言った、「あなた、前をみなさい」するとそこには、輝くあれが。
ジョーは又、別の景色を見ていた。彼は「疾」についてなんて、考えない。だって漢字を知らないから。だから、「running!」と考えていた。考えているのか、考えていないかも、わからぬまま。
ふたりは、内緒だけれど、つき合っていた。
we're runnin!
タローはシャイなので、うつむきがちに
そうね、ラニン……
とぼそりと言った。
そんなタローをジョーは「so cute!」と思った。ああ、夜が待ち遠しい。既に夜なのだけれど、ホントウの夜はこれからだった。息を切らして二人がついたのはネオンサインが輝くリバーサイドホテル。ラストスパートでフロントに辿り着くと、ふたり、一部屋、カオの見えないフロントに、そう告げた。
フロントは、どうも二人が男同士な気がするので訝しげにしていると、タローはくにゃり、韓国人女性の真似をして、「소녀들의시대가왔다(少女たちの時代が来た)」、ジョーに体を預けながら言った。するとタローが健康そうな女性に見えたのでフロントも安心し「301ね、ごゆっくりね、朝は12時まで、そのあとは1時間千円ね」と応えた。あと少なくとも10時間、二人はくっつき合う。
でも最近、タローは段々女の子みたいになってきた。何か薬でも飲んでいるの。どうして、心なしか肌も柔らかく、服装もくにゃくにゃしているの。ジョーはタローの、男に惚れたの。
ああ、河だ、向う、河
ジョーはタローに、お金を借りたの。
百ドル札、必ず返すから、口座番号をメールで送って。そう言って、もう10万円くらい渡しているけど、仕方ない、詰め寄られて、タローはジョーにお金を貸した。ジョーは、お金が無かった。すぐお酒を買ったしドラッグも買ったし、妻と娘がいた。
『白い散歩』
真っ暗な中、真っ白な外に出ました。まっ暗かと思いきや、街灯もない山の中は意外な明るさでした。
雪がふっているからでしょう。雪は月明かりをいっぱいにたくわえて、辺りをぼんやりと照らしていました。
都会育ちの私らは、吹雪の中歩きました。セブンイレブンを探して。
明るいとはいっても、やっぱり山の中。しかも都会育ち。
私は、一歩一歩前に進むのが、怖くてしかたありませんでした。
ふりたての雪はまっさらでなんの痕跡もなく、雪というより、もやのように見えました。
歩きながら2人は幽霊みたいと思いました。突然視界に広がる景色は、あんまりこの世っぽくありませんでしたし、このあたりに住んでいる人が、大雪の中、手をつないで歩く2人を見たら「あ、おばけ」と思っただろうと思います。
幽霊のよう、と思いつつ、私は、自分の足あとを決して忘れてはならないと、こっそり誓いました。
途中、何度かふりかえり、来た路についた4つの足跡をかくにんしました。
幽霊の足あとは頼りなく
続いていきました。
このハナシ、知ってる? ジョーはタローに言いました。
タローもジョーに言いました。
僕らもあれだね、ユーレイみたい。
ユーレイは2人、夜のすき間に重なり合い、肉欲を満たしていきました。2人こうくっつき合って、飽きることなくさすり合い舐め合い、ドウブツみたいに。その姿は、雪の中のユーレイのよう、ぼんやりと、白い影みたいで。ドアが閉じる、灯りが消える。
朝が来たら、ドアが開きました。
タローは路上にいた。路上には、いろいろな人びとがいます。それは片隅で寝袋もしくはボール紙にくるまって寝転がってる人ばかりではなく、そこで煮炊きをして家族ごろりと棲んでいる人ら、おぉいあのすいませんが……といって千円の商品券と引き換えにアンケートを募る人ら、もしくはあはぁと言って募金を募る人ら、ただただタムロしてる人ら……けれど、待っている人が一番います。恋とか夢とか抽象的な何かをずっと待っている人。それか単に待ち合わせをしてる人。それか、歩いている人。ただただ歩いている人や、どこかに向って歩いている人。
タローは、ただただ歩いていました。歩く事、ただ歩く事。明治通りに沿って、どこからどこまで? タローは今、ひとりでした。比喩ではなく本当に。ジョーはあの日、お金を置いて逃げました。はるか遠く、雪のない国へ。タローは別に、そうか、へえ。と思いました。比喩ではなく本当に。それきりへえと思ってるばかりです。
歩いているそこは、広尾だった。外国の重要人物たちが集う故、外国そのもののようで、路は広々、公園も広々、草木も一杯、カフェーがある……など、だからヘンにセレブリティのように見えるのかもしれない。別に広尾を弁護するわけではないが。
タローはまだ、20を過ぎたばかりだった。楽天的で、また別の男が見つかるさと思っていた。と、歩いているとおぞましい雰囲気がした。眼の端に闇がわだかまってるようなダークな臭気。レストランとカフェの間、白い戸の前に異様に真っ黒い黒ずくめの男がいました。何か、ぼそり、ぼぞり、彼の頭の中に直接話してるように響く声を発しているのです。何を話しているか、分からない言葉で。けれど、これは未来の自分では? 彼は何とも言えず直感しました。だから口を抑えて、通りを早足に、逃げた。くぐもった声のトーンだけがうすく、頭の中で反響していた。
明くる日私らは中華に居た。あんなにまとわりついていたビニールは、きれいに解かれていた。
ここは、特別な中華だった。あまりに効果が絶大なので、予約するのに政府の許可がいる。許可をとるためにはコネクションがいるのは中谷さんのお祖母さんがとってくれた。
コネクションが無い人は、嘘でも入院していないといけない。廊下にいかにも健常そうだが、服をきたままベッドに挟み込まれ、半ばしかめ面をし、しかし楽しみそうに順番を待っている人がいるのはそのせいだ。とくにしかめ面をしているのは、初老のタフそうな男性で、眉が波打ち、への字が二重になっている。一緒にいる女性がここの料理を食べたくて、無理に連れてきたのだろう、ああ言ってこう言って。女性はへらりと笑っている、なかなかしたたかそう。長身でどこか少女のような可愛らしい風情があって、すらりとした足、うすい胸、比べてすこしボリュームのある腰。2人はそうやって長く連れそっているのだろう。
ぼくらはコネクションがあったので、そう待たずに大きな円卓に連れて行かれた。窓からサインが見える、ちゃかちゃか変わるネオンサインだ。サイン、サイン、日々はサインで溢れている、日々どころか景色も合間を見つけてはサイン、サインの氾濫がしている。見ようによっては秋空さえサインだ。
見て見て、何というかリズムが、飛んでくるよ、景色から。
そんなことより中華を見るべきだろう。こうまでして中華に来たのだから。
最新の夢
テレビチャンネル、
サイレンのひびき
ため息までがフー
お茶まで熱くてフー
みんなで食べる
ステキなチャイニーズフード
今のは偉大な音楽だった。それで私らは、約束された中華を食べた。四人で、約束された葉っぱを炒めたのと、たまごをふわふわにしたのと、麺。合わせて三千円。紹興酒のボトルも飲んだのに格安で、中華の奇跡だろう。
私らはそこそこにテーブルを立ち、あのカップルに席を渡した。
店を出た。坂が多く、石で組まれた路面。まさしくそうなのだが、中国と英国が折衷したような香港の街並は、歩いていて面白い。黄色っぽい薄灯りのもと、四人でよちよちと歩いた。約束された中華の効果か、歩く足取りも軽いようだった。景色も何か、いつもよりクリアに映るようだった。
*
追いすがる、じっと見つめる。フッと何かがよぎる。ざらざらと心もとないフラットな空があって河があって、全体にぬるぬると継ぎ目が見当たらない。
ウシがいる。ウシは意外と垂れている。皮がびろびろと、もたもたと落ちそうで落ちない滴のように、顎から前肢にかけて、前から後にかけて。これから先もこれまでも、動くことなど知らないし、聞いたこともないという風情。路上、ごちゃごちゃの激しい色、陰鬱な食堂の店先、路地の奥、線路の上、垂れているし、垂らしている。蛇のように首をもたげ、もしゃ、もしゃとビニル袋をしゃぶっている。喧噪の只中、ベース音のように。
ネコも意外と垂れている、顎とか腹とか、そう尻尾とかが。ミャウと言って右にブれ、ミャアウと言って左にブれる。格子の隙間から覗いたネコはそうやって、ああ、いるんだかいないんだか、ブれると見えて、ブれないと見えない、気づくとひょいと姿を消している。影も残さずに。
向うの影はぴくりともしない。ウシは意外と垂れていて、滴が垂れて垂れ落ちそうになる。たまにぽとぽとと音がする。かと思えばやっぱりそうでもなくて、意外と激しい夢を視る。つぶつぶとフラットな空で、それが体に入ってくるようで、虚しいような、白けたような……。ウシは意外と垂れていて、耳は垂れてしかし目蓋は垂れず、ぎゅっとしてぶるぶると揺すったり涎を垂らしたり。意外とアブない夢を視て、ぶわああと哭く。
…のさ…
その夜、抽象的な電話をしていた。ここで牛が尻尾を揺すった。一回……、二回。
…ッパのユニ…ロで…、…グラスを…ったんだ…
牛が首を、振った…。何のハナシだったろうか。ひとは延々話し続けている、私は相づちをうつばかり。
でさ、
通りすがりのパレードが爆竹を放り投げた。足元で爆ぜ、牛が電気が通ったようにオレンジ色に発光する。牛は目蓋を…閉じた。また爆竹。今度は青に発光。目蓋を…開いた。パレードは去った。黒い目が中空を見つめる。通りは砂塵が舞い、騒音は他人事のように鳴り響いている。右脚が…そろりと上がった。場所を移るらしい。足元から爆竹のケムリが上っていく。オレンジと青がぐにゃぐにゃと混じり合って、夕空が安っぽくボけている。牛の発光がまだ残像している。
あー…、
…い…紙に、ロファンが……てて…
ケムリが去りゆく。
…の…が、まわって…、
牛はそこらで立ち止まり…また瞬く。眠いのだろうか。私も眠い。タバコに火を点ける。
*
机とイスとテーブルがあって、いや、机とテーブルは同じものだからイスとテーブルがあって、それだけのシンプルな空間で、壁は赤、あなたとむかい合って座っていて、ただ何となく、ビールの小びんを、あなたはコーヒーか紅茶を飲んでいる。歩き疲れここに落ちついたのだった。
壁が薄いのだろう、となりの部屋では、何か女優が一人芝居をしているような雰囲気がしている。その人の声しかしない。けれど静かな喧噪がしている。その人の声は抑揚がきいていて、時に大きく、時に繊細に発されるのだが、どれもこう、クリアに聞こえてくる。素人ではこうはいかない。それにそれは英語だ。
リップクリームを持っていないか
私はポケットに入れるクセを止して、ポーチにいれるようにしている
あなたはカバンからポーチを取り出し、その中からリップクリームを出した。
リップクリームを唇に塗った。それで、タバコを吸おうとひとつ口にくわえると、ドアが開いて男が入ってきた。部屋にはテーブルやソファがもう少しいくつか、並んでいるのだった。男はその一つに腰をすえた。目配せをすると、暗がりからもうひとりやってくる。お冷やをテーブルに置いた。
ご注文は!
リップクリームを
男はジャケットのポケットから、折り畳んだ紙を取り出し広げる、もう一つのポケットから、虫眼鏡を取り出しそれを使い、その紙を観察し始める。もぞもぞと口に出して何か、読んでいる。それはどうも、辞書の一片のようだった。タバコの煙がもうもうと部屋に流れている。あなたはじつに眠そうになっている。
となりの部屋の喧噪がずいぶん大きくなっている。音量はさして変わらないのだけどその雰囲気が色濃くなっている。クライマックスだろうか、女の人の声が悲壮さを帯びている、打ち震えるように。すると芝居が終わってごやごやと人らが出てきて、さ、一休みとこの喫茶店に入るのではないだろうか。沈黙を打ち破るように客たちは言い合いをするだろう。テーブルには酒のコップがぎっしりと並び、はては下世話な話もするのだろう。
外はうすい雨、風が強そうだ。
出ようか。
出て、どうしようというの。
次は、どこへいくのか。どこへいっても同じじゃないのか。
いや、 にいこう、このままこれから
また、そんなこと言って、パスポートも持ってないのに
じゃあ、笹塚にいこう
そうね、笹塚ならいけるかもしれない。でも笹塚に、何があるというの?
えと、何か、スラムのようなふんいきの駅前と、ボウリングと、ご飯屋さんとか……そこそこに、気の利いた、一人暮らしのひとによさそうな、すこしシャレた、都会的なようなそうでもないようなカフェとか、妙なインド屋さんとか、あとそうだ、奇妙なホテルに住んでる友だちがいる
……お家に帰らない? わたしは眠い
その頃笹塚では、奇妙なホテルの一室にメガネをかけた奇妙な男が住んでいた。
ホテルの空き室を賃貸しているところを借りている。絨毯のゆかには電熱器が置いてありその上にフライパンが乗っている、そして目玉焼きが焼かれているのだけれど、ホテルの事情で電力は弱く、まだ生からそんなに姿を変えていない、隣にはトースター。食パンがささってはいるが電力の事情でまだパンはトースターの中には入っていない。
彼はさっき起きたのだった。目玉焼きとパンを尻目に、置いてあるDJブースの上で何やらレコードをいじっている。音を出そうとしているが、まだ出していない。クラシカルなスピーカーが、机の上に据えてある。
恋人が来ようとしているのに、備えているのだろう。
「小さい時は、アメーバ状でした。それで、お祭りの日に山車の後に皆ですわって、太鼓を叩いた。大きな太鼓は、大輪の花の、大きな葉のようだった。叩いているうち、うしろにころりと、転がり落ちた。山車は前に進んでいった。アメーバ状だったから、痛くなかったし、特に覚えてもいない。そうして、大人になった私らはゾルゲル音楽をつくった。アメーバ状の人びとを保存して、いつまでも楽しめるように。湖に垂らたり、フラスコに入れて吹いたりする。私らはうっとりしたり時に笑ったりして見ている。それは水面をたゆたうように広がり、水中に垂れゆくのか垂れないのか、微妙なところで留まり続ける。いつまでも続くイントロダクションのように空間を満たす」
*
展覧会にいって絵を見たいなあと思うと、もういつも閉館が過ぎた時間。
道を行く、そっと目を壁にやる、大きな絵がある。白い空間、ライトグレーの、打ちっぱなしの壁。
ゆっくりと歩みを進めると、右に、左に、数歩ずつ間合いを置いて、絵の力に応じて、程よく配置されている、すてきな柄のように見える絵や、写真みたいに写実的で、けれど面白くない絵、モチーフの不在、不在、不在……そう思いながら見ていると、思考の余地を与えない、描き手にとり必然に生まれたとしか思えない、素晴しいものがある。ああ、これを眺めていよう、そうして立ち止まる、近くに椅子があればなおいい、見ているそれを見ていて閉館まで過ごす。
え、何でいるの、どうしたの
すいません、待ち伏せしちゃいました!
飲み屋に入ってきた女性が、先にいた男性たちの輪に入った。店はさらに賑やかになった。自分の外側で。隣の席では、めがねの女性がひとり。男が、相席をいいですか……といいながら気づけば、女性を清々しくナンパしている。すこし嫉妬……うつむきながら、ペンを走らせる。
あるいは、知り合いの作家の展覧会に終り間際に走り込んだりする。うまい具合に、作家はいない。こう時間がないのに悪いなあ……そう言われながら、こう見る時間を考えずに来てしまった自分を、とても悪く感じる。そうしたことがないし、何より、いい展示ならいいけれど、よくない展示なら、その反応をさとられる。それは悪いことではないけれど。
何かホタルノヒカリのような音が始まるので足をあげ去ろうとする、すると曲がり角、その奥には、例の抱き合う二人がいる。「ねえ」「好き」なんてどれでもないだろう、ただうろんとこちらを見つめるだけ、見開いた目が。
中谷さんはまだ雑巾がけをしている。
ちょっと待って、ダウンロードしている。クラウド時代だから……。
彼は右から左に白い絵を描いた。先っちょがふわふわとした大きな刷毛を持っている。すごいスピードで刷毛が動く。描かれているのはアヒルの顔、すごくうまいが独創性はない。けれどその大きさが独創かもしれない。120mはあるだろう。工事用のゴンドラに乗って上下しながら壁に描く。助手のような人が片隅に窮屈そうにしゃがんでいてゴンドラを操作している。
そうしてまたたく間に顔を描き上げました。そうして今度はまたたく間に絵を拭い落としました。あとに残ったのはただの白い壁。白い中、彼と助手を載せたゴンドラがゆっくりと余韻のように上下しています。
それを見て、今度はウィンドウを見る、きれいなガラスで透明で、何かマネキンが立っている。一匹の葉のような虫がくっついている、ちょうど真ん中に。
はらはらと霧雨が降っていた、黒い服を着ていたからいくら雨粒が当っても気にならなかったのだけど彼女はそれがとても厭だったみたいで途中のコンビニで傘を買ってくれた。私は少しうつむいて雨が目に入らないようにしながら傘をさして歩いた。
歩く、歩く、歩くと強度が増す。あたまがこう、一点にまとまってくる、とものの本にあった。
彼女と遠くを歩いたときは、とてもストイックに線路を歩いた、海沿いを歩いた、雨が降ってびしょびしょになりながら荷物を抱えてちょうどそこに民宿があって素泊まりをした。腹が減った、何を食べていたのか覚えていない、きっとコンビニのおにぎりか何か。どっかローカルな程遠い駅に降り歩き出して1日目、2日目、そうして過ごして、それで3日目少しズルをして電車に乗ったらどうも凄い都会に着いてしまった。ああ、ぽっそりした気分になってシティホテルに泊まった。なぜだか味わい深いしつらえで、すこしカビくさい感じで今でもその雰囲気を覚えている。それで朝、浜に出て、こう、おじさんに道を聞いて、また歩いて……。目的地はどこだったか。
見知らぬ町に霧が踊る
彼はその間に手紙を書こうとした。
ひとり芝居を終えた女がいた。名前はセント・J・マル子。とあるアパートの一室で芝居をしていた。薄い壁をはさんで、隣の部屋は喫茶室になっていて、そこで一服している。15人ほどの観客をまえに、英語で、淡々と芝居をした。その部屋はそうやって使う部屋だった。それで観客たちはとなりの喫茶室にお決まりで滑り込む、でもマル子には特に絡まないし、芝居の感想なども口にしないのが暗黙のルールだ。そうしないとコーヒーが不味くなる、と壁に書いてあったから。マル子は粛々とコーヒーをすすった。
とても好きだよ
そう一行したためて丸めて捨てた。すこし苦笑い。
ご注文は? 恋にしますか
きかれて彼は、恋に落ちることにした。そうしてまた、目がさめた。そこは白いバーで、隣にはやせた女性がいた。胸を半分剥き出して、とても柔らかそうで、上質の餅のようだった。
お試しなすって、女はそうおどけて言った。試そうじゃないか。寝起きでハイな男はすっきりした声で言った。実はそこも興奮していた。
試そうじゃないか、今度は何か真摯な体をよそおって言った。2人は即興の恋をした。
クルマは悲鳴をあげ2人を連れゆく。女は胸を半開き、男は口を半開きのまま。乗合いタクシーなので、隣にはまた別の男女がいる。中にはたまらずまぐわう奴等もいた。目を背けた。小さく喘ぐ声。まさぐるヒゲ面。むき出しにされた女のももを盗み見た。
2人は雪国にたどり着いた。車で30分。いま2時2分。温泉で有名な土地だったが、もう遅く何処も門を閉ざしていて、運転手が気を利かせ2人をラブホテルの前で降ろした。乗合いの皆は温泉を予約していたので、さいごの2人だった。
ガラス張りの風呂で女はおもちゃで遊んだ。男は童貞だった。見て見ぬ風を装い女のそこやここやあそこを覗きみた。覗きみられ女は体をほてらせた。
寝ようかね、しれっとしたフリで男は言った。女のからだを何も知らない。とりあえず手の動くままに大事なところ以外をまさぐる。女は男を見透かしていた。心臓の音が重なった。女は体を火照らせた。男もそこを火照らせた。女の手がそれをそこに導く。夜に溶け合う。
溶け合った後も抱き合っていた、ぼそり女が、子どもが出来ちゃうかもと言う。女は結婚詐欺だった。だけどこの男には惚れてもいいかもしれないな、可愛いから。だけどいつものクセが顔を出した。男はどう応えたらいいのか初めてヤッた気持でいっぱいだから、分からないから黙っていた。それは何か正しい反応のように見えた。
ねえ私たち結婚しない? 女は本気だった、第6感がそう言っていたから。男はやはり黙っていた。大丈夫だろうかアタマは、と思っていた。朝、男はこっそり帰った。連絡先を書いたメモを残して。
そんなことがあったんだ、男は話した、半年後夏のビアガーデンで。心を許した相手だった。
その夜はひとり帰った男はあの女に電話をした。今でも月に2回電話があった。知って知らぬフリをしていた。俺は何て勝手な奴かと思いながらふと、あの女と話したくなった。女は電話に出なかった。次の日も始終かけてみたが、繋がらなかった。月2回の電話もそういえばさいきん無かった。
急にあの女が気になった。あの日の雪国にもう一度行った。それが次の次の日の昼間。特急に乗ってるあいだ男は一冊のカワバタヤスナリを読んだ。それは被爆した家族のハナシ。桃の汁を一年半ひたすら飲み続け生きながらえたおじさんのハナシが妙に気に入った。一刻も早く桃を食べたくなった。そうだ女と桃を食べて女の桃も食うんだ。麦酒と電車の単調な揺れでほろ酔いの頭でそう考えた。頭の中はあのベッドで一杯だった。
男は店を探した。あたまにうっすら残る白いバー。うすうす感づいてはいたが、記憶に無いバーを見つけ出すには、どうしたらいいのか分からなかった。あの日それまで彼は何していたかもボンヤリしていて記憶にない。男は酔いを深めながら街を彷徨う。昼の町、夜の町、あの時一瞬でもあった人に会えればいい。小さな町だから会ったらどうにかなる。彷徨って2日、3日、1週間。その日、ある喫茶店に入った。そこは散々探した中で最後の一軒で、すすけてヤれてどうしようもない小さな店だった。はいると見知らぬ女が宿り木に腰掛けている。
というか宿り木に女がひとり腰掛けるだけで一杯のお店だった。カウンターに向っている女は、こちらを首だけで振り向き、品子を探しているのね、第六感でわかるわ、と言った。品子は結婚詐欺に失敗してほんとうに結婚してしまったわ、結婚詐欺で貯めたお金でいまは男とホノルルに居る。しかしどうだかね、わかりゃしない、あの人はどうしたのかしら。
R’階段。真四角の札に赤字でR’と書いてある。そういう店の看板だった。同じものを見たことがある、新宿の地下で、あれはじっさいにそういう階段の名だった。その階段のところはたしか、右と左上がる階段があって、その真ん中の踊り場に看板があったのじゃなかったか。
そうです、その踊り場とちょうど同じ広さだから、それにちなんで店の名前にしたのです。私はよくあそこで、オーボエを吹いていました。まだあの道が出来たばかりのころ、70年代だったか、いい時代でした。隣には靴磨きがいた。
僕の心を読んで、暗がりにいる店主がそう言った。
品子と私の思い出の場所なのです。いい時代でした。
東京に帰ると僕は放心しぶらぶらと新宿のそこに行った。
と、ひとつめの街に着いたときは、道連れがいた。彼とは電車を降りる時によくわからなくなって別れた。どちらにせよいっしょに歩くのも面倒だなあと思っていた。そうしたらまた会った。
彼は、いかれたライマーと一緒にいかれたライマーになっていた。
よぉひさしぶり
あァひさしぶり
ぃよォ
あン
いやぁ
そう肩いからせながら言い合う二人は実は主張の無い男たちだった。ゆえに流されるままによしとして生きている。撫でられるまま、さすられるまま。けれど、ここは一歩引けない! そう思った事があった。何も答えようがない願いを聞いて、どう答えたらいいか、自問していた。
私は、はじめまして、私は、どうしたらいいか、考えています。昼からしじゅう酒を飲んでは文字を打ち込み、打ち込み、繰り返して。
彼は、何をしているのか。わからないけど、叫んでいて、それは文字通り叫んでいる、のではなくて、絶えず叫びを目玉から感じる。つまり、びっくりしたような目をしている。ひとに聞くと、それはレーシック手術によるものだった。失敗したわけではないが、あまりうまい医者じゃなかったから、瞳だけでなく目蓋にもしわ寄せがいった。メガネがアイデンティティだったような自分に倦んで、目も悪かったしそうしてみたのだけど、彼はしばらくしてまたメガネをかけはじめた。は、は、は、高らかに笑う、彼の目は前からそうだがわらっていない。
何をしているのか、ここで一体何をしているのか、考え出すとわからないことばかりだった。そうしている間に楽しかったり大変だったりするのだけど、そろそろそう、決めなきゃいけない。小説を書く周期は10年ごとにおとずれると何かの本で高見順だったか言っていたよ、と書いてあるのを読んだが、ものごとはそういうところがある気がする、ようは、アウトプットをどう出すか、けりをどうつけるか。
ごらん、彼もこのごにおよんでドキュメンタリーをしている。変わっていくね、変わり続けているね、でも書くことは変わっていない。書くことを選んだことはね。
彼はメガネをそっと外し、パーカーの袖でぬぐった。いつか言ったものだった。
フード社会だからな
フード社会とはつまり、誰もがフードを被っていてそれが当然という社会だった。社会は小さくもなれるし大きくもなれる。ひとがいれば。ひとを認めれば。
*
奥が店になっている。向って右側の部屋。壁には壊れた傘、子供用の衣服のような派手な色の布、それとラクガキがたくさん貼ってある。そこにたむろする子どもたちが描いたのだろう。床には、円いイスのようなもの。それでもう一つ、藤椅子のようなもの、子どもがいつも座ったり転がしたりして遊んでいる。私が滞在している間ちょうど、この部屋に念願の大きなソファが入った。民家から皆で運んだ。
真中の部屋は大きなものはないが、人びとが何か作業をする。イモを焼いたり、ニンニクを干したり、何か書いたり、機械を触ったりしている。だから子どもは入りづらいようだ。あと棚のようなものに、不通のデンワ、錆びて真黒になった地球儀、錆びた箱などが置いてある。あとはカゴが少々。これは人びとが背負っていくカゴ。
不通のデンワで遊ぶネパール人の女の子がいる。「もしもし、もしもし」言うと彼女が応答した「もしもし」
子どもたちはどんどん膝や手足に集ってくる。まとわりついたり、慌ただしい。
真中の部屋では通訳がおばさんと話し込んでいる。何を話しているかは勿論分からない。彼は先ほどまで大きい記録帖のようなノートに書き物をしていた。その部屋の片隅にはドアがあり、その先のバックヤードは外界から隠されていて、電子機器などがある。真ん中の部屋と左の部屋の間の壁には、大きな地図がある。
左端の部屋には、服が沢山置いてある。ここが一番店と言えば店っぽいが、少し持て余しているようだ、あまり使われていないらしい。真ん中に足ふみミシンがあって、そこに犬が寝そべっている。
こう、しゃがんでいるだけでもあっちから何か来たり、こっちから来たりしています。でもしゃがんでいるだけでも陽射しがよくて、そこだけ違う国みたいだった。
その日はそうしてずっと歩いて、いろんなことがあって、ゆくゆく帰っている。たんたたん、と電車が行く音。遅い電車に揺られていると、取りとめなくぼんやりしてしまう。窓の外は、曇っているのかそれすらもよくわからない、何もない空。明るいものは線路や電線くらいで、相変わらず黒い。頭の奥で、まだループしている、あの地下道の空気と、街のざわめきと電車の震えと、散り散りに。そのまま頭を窓にもたせかけて目を閉じていると走る音はゴトゴトとまた戻る、家に近づいている。
車内は妙に混み出してきた、人の気配がごじゃごじゃしている。妙なグルーヴがこだましている。さっき見たおじさんと地下道の残像がうすぼんやりした頭に軽妙によぎる。
意外と長い地下道の、向うの角に男がいる。箱を縦に構え、バイオリンの弓のようなものでそれを撫でている。箱には無数の弦が張られていて、よく見ると祖末なアコーディオンのような見た目で、一見するとゴミ、それを鳴らす男はゴミ箱を抱えた路上生活者のよう。けれどゆるやかで迷いがない動きをしている、奏でている。楽器のケースだろう、男の足元に置かれたフェルト地の黒い箱には小銭や缶コーヒーがちょぼちょぼ入っている。男はゆっくりと弦を撫でたり、空いた指で他の部分を弾いたり叩いたりしている。楽器はひとつなのに色々な弦が共鳴し地下道の壁に木霊し、沢山の響きが散っている。豊かな音色は、ずっと鳴っているような、鳴っていないような、静かなのか、喧しいのか、不思議な案配で滲みてくる。
景色を電車に戻すと女がいる。ドアのすぐ傍に立っている。素っ気ない素振りで長髪、すらりとしていて、左手に持つビニル袋のなか、鮮やかな果物がのぞいている。長細い指、しなやかで透き通っている。次の駅だけで、女の傍のドアが開く。リズムがゆるやかになって……停まる。弾みをつけドアが開く。ゴヤゴヤとうるさい。女は、人混みなど知らないみたいに、すうと出て行った。
大人というのはこうやって別れるものだと思っていた。去り際、ドライに淡々と言う「愛してるよ」。すると、
え、愛してるの
目を見開いて、女は戸惑ったようだった。それでそのままだった。大人というのは、映画みたいに、こう別れるのだと思ったのだけど。女の言葉が気になって戸惑う。
え、愛してないの
いや、まあ、言えば、愛してるけど……、
あたまの中でもぐもぐと、会話を転がす。
彼女は人が苦手だった。それでいて室内も嫌いだった。けれど生まれたところが都会で、あまり遠くに離れるのも気がひけた、祖父母の遺した土地もある。けれど、中にいると段々息が詰まる、3、4時間くらい居るともう歩き出したくなる。だからなるべく夜行性の生活をし夜の中に抜け出した。けれど人が恐くて仕方ないから、なるべく人に見つからないような地味な格好をした。路地裏。いけない狭いし人も近い。校庭。いけない夜は閉まってるし捕まるだろう。
私が0時過ぎ道を歩いていて歩道橋をのぼると、女性が屈伸運動をしている。橋のちょうど中ごろ、車のための大きな青い看板のうしろに隠れるようにしている。右、左、背筋を伸ばす。次は腰、右、左。朝の太極拳の人みたいなすがすがしいような身振りだが、帽子をかぶりマスクをしていて、どうしたって爽やかでなく奇異だ。興味をひかれしばらく遠くから眺めていた。けれどどうもこう、人が恐いんだろう、過敏に周りを気にしているようだったので、素知らぬ素振りをしてそのうち歩き過ぎた。その先階段を下りる途中で振り返り見ると何故だか看板に隠れたのか彼女のすがたは見えなかった。
まるい目をしていた。白目がきれいで、きょとんと瞳が動いた。何かリスか何かのキャラクターみたいに。それがとても、可愛らしく見えた。これは何か出合いだったのかもしれないなと感じた私はさもしいのか、それか彼女が寂しそうだったのか、いやまあヒマなんだろうな。
彼女としては、いつものように大きな道の歩道橋の上で屈伸運動(これは一日一度、0時過ぎ)をしていると、どうもあちらからうかがわれている気配がしていた。私は他人とからだを触れ合うのは嫌いだが、そうは言っても恋をしたいので何となく男性を意識することもある。こういうタイプが一番えろい、そう言われるかもしれない。近ごろはネットもTVも雑誌も見ないからわからないけれど、そういう話を高見順の小説で読んだから、きっと今もそう変わらないのだろう。
それが二人の出合いだった。
夢の中で、私は崖の苔になっていた、というか、ずっとそうなのだった。ゆえに意思などないし、言葉なんか知らない。
けれどお前、言葉を発している。
そう言うお前の言葉を私は発しているだけ、鏡のように映しているだけ。私が何か見ているのもそうだ。お前が見ている景色を見ているって思われているふりをしているだけ。春夏秋冬、春夏。変わらず私はへばりついている、崖の突端、それを少し越し、逆向きの坂になっているところ、眼下には海がざぶーん、ざぶーん、としている。たまに漁師がたむろする、タコを釣り上げたりしている。そうしている間に季節がかわる、秋風がふいて寒々しい。
あ人が
つかの間、落ちていった。一瞬手足が見えた。もう打ち上げられている、ざぶーん、ざぶーん、と。それでまた季節が変わり、私は茶色っぽくなる。また季節が変わり、私は青々と繁り手を伸ばす。
またたく間に広がる、
見えるものが違う
カーテンを開ける、
すると陽がさす
濃い何か四角い影が先の壁にうつる
*
ライブの始まるときって、こう緊張感が段々盛り上がってきてさ、おしているともっとこう高まって、待ちかねる! って風情で拍手をして待ったりするね
そうね、芝居もそうね。大きい芝居。小さい芝居だともっとオーイまだかー! と声かけたりしてね。あ、店員さんが来ちゃった、じゃあまあ、何か頼みましょうか。
せっかくだからね。
二人は例のマル子の店が気に入って、また来ていた。今日は、隣に入ってみようと思っていた、あの芝居小屋に。店員さんにさっき聞いたら彼はぼんやりしていて、よくわかっていないらしかった。インターネットで検索したらあれがマル子のやっている小屋と喫茶で、芝居のおわったマル子がコーヒーを飲みにくるらしい。けれどマル子に声をかけるのにもこつがあって、決して、知り合いでもないのにマル子さんと呼んではいけない、ほんとうに素知らぬ素振りをして、あのすいません、と声をかけないと相手にしてくれないという。
だって私はただの人だから。あなたもそうでしょう、芝居をしている。人はすべからくそう。と、インタビューで応えていた。
あのすいません。
あなたがマル子に唐突に声をかけた。私はマル子がいたことすら気づいていなかった。女は役者だと思った。
はいはい。
隣ってお芝居をしているんですか? こないだ来たとき、ごやごやしていて、魅力的で。
はいはい。そうですよ。見にきますか?
え、はい、少し……。
何が少しなのか分らないけど、とても筋の通った受け答えだと思った。お勘定をして、店を出た。
このお店にも通い慣れてきた。小さなアパートの一階の隣り合った二部屋で、出ると、ふつうのアパートのドア。それで隣の部屋にマル子が案内してくれる。
ばっ、とドアを開ける。ばっ、と照明が灯る。待ちわびている観客たちが10名くらい。それを横目に見ながら入ってすぐ右手の音響さんのところにある梯子を昇って、足場を歩いて舞台裏へ行く。
よォ、リスン
小声でマル子が言って、そこに置き去りにされた。聞け、ということなのだろう。私どもは小さくしゃがみこんで、そこの舞台の上手の上部から舞台を見ている。拍手とともにレッドカーテンが上がる。芝居が始まる。
今日は一人芝居ではなく、マル子ともうひとりの女性による芝居だった。途中、アヒルの玩具が出てきたり、とある映画監督のそっくりさんが垣間見えたりと、シュールな小ネタが存分に効かされた内容だった。正直、わたしとあなたは、拍手をしかねた。まあ、面白かったけど、3時間半はちょっと……という芝居だった。
あなたねえ見て、ホドロフスキーも見に来ている。
誰
きれいな顔をしたひと
まあ、ごやごやと出てくるお客さんたちとともに、出てきて、ともに隣の喫茶に入り、ビールを飲んだ。マル子はそこに座っていたけれど、とりきめ通り、私たちは彼女を気にする素振りは一切見せなかった。彼女もそれでいいようだった。
共演者が、見にきていた知り合いと談笑している。そういうのはいいらしい。そういうのとはこう、芝居と実際を混同すること。というか、彼女もただのお客だったのかもしれない。どこかそんなふうだ。地方から、出てきたらしい。右手に東京ばななの包みを持っている。
喧噪がだんだん、高まってきた。おじさんたちやおばさんたちの声。彼とか彼女ということばは恣意的だと思う。というか男性を彼女と呼んでもいいわけだし、女性を彼と呼ぶこともある。彼女はつまり、おじさんだった。よく話を聞いていると。声は中性的なのだが内容はおじさんだった。やっぱりただのお客じゃなくて役者だったのだろうか。でも役者って何だろう、お客って何。
出ようか
出て、どうしようというの
へ行こう、このままこれから
またそんなことを言って、パスポートも持ってないのに
いや、ここにある
あら何よ。じつは私もここに
ほら、うまい具合にそこに成田行きのバスがいる
いいわね、乗りましょう
席が空いてる
酔っ払いが多いわね、みんなぐっすり寝ている
五反田行きだったね
田しか合ってないわ
五反田には、淡々としたカフェの店員がいた、おかっぱ頭に丸めがねをした、音楽的な佇まいをした男。淡々とジャズを流しながら、珈琲を淹れている。彼はそう見えても疲れていた。よれっとした頭を揺すりながら、ようやく家に帰ると、絵を描く。レコードを逆回転で流す。ブルーのインクを水墨調に扱い電球やジャズメンを描く。ぽたぽた、垂れる水滴が絵に見える。
彼は水辺があるとそれを眺める、生える草を撮る。右から左にくまなく撮る。
そうして日々を繰り返す。
書き割りの舞台が空いてその先は神社の境内になっている。クライマックスで男は何かを捧げ、捧げ持ったままシューと後にスライドして舞台の向うに突き抜けていった、同じ姿勢で。したに車のついた板を押す黒子たちがいる。奥の方で何か女性と立ち会っている、捧げ持ったものを渡す。暗くてよく見えないが、どうも貝類のように思える、大きいから、ホラ貝か。
自転車が沢山飾ってあって、そういう展示で、その前に人びとがたむろしている。二人連れで皆さんお越し頂いていて、皆自転車をみるわけでもなくイスに座り語り合っていて。でもまあそれはそれで場が和むし茶は売れるからいいか。そもそも展示のための展示じゃなくて、この新しい自転車をプロモーションするための展示だったから。でも見ろよ、ソークール、オレンジのアンプのロゴを代理店の許可をとって貼り付けた、ロックスターの自転車。
洞穴を前から見ていたら、風が吹いてきたのだった。洞穴。江ノ島に洞穴があって、それを覗いたことがある。風が吹く、前から吹く。髪はバサバサになっていた。
あるいは、抽象的に描いていて、もうぱっと見何が何やら分らないけど、ぐっとこれは海の洞窟だ、と感じた絵がある。穴居する人形がある。人形は言った。あなた、前を見なさい。前は絶壁だった。
夏みたいな青空がすごくて、すごいなあと思いながら電車に乗っている。ひとはいないし、ただただ窓の外が広い空で。
と思えば喫茶店で喧噪がしている、10時過ぎだというのにうるさい。となりでは住宅業の人びとが何か打合せをしていて厭でも耳に入ってくるがどうも気になってしまう生な情報だから聞いてしまう。
いや私は、河があって、それがよかった
いや私はそれよりもこのクッションがすごくて、もう……
そういう芝居だった。そこにカーテンコールの女が現れる、貝を持って。これはきくらげ、これはしじみ……
波がざぶざぶと、よせてはかえす。ざぶ、ざぶ、砂を巻き込んでワカメを垂らして。
そこを二匹のイヌが、われさきに、いやわれさきに、といった体で早足に駆けていった。イヌの早足は足がとてとてと高速で動くのでかわいい、と誰かが言った。
私はタローとジョーの二人を、思い返していた。
イヌの間をどっしりとしたご主人が歩く。それもまたすこしかわいい。
気がつくと、一年も二年も過ぎているように思えた。けれど一日か二日か、あるいは一秒か二秒か、まったく過ぎていないようにも思えた、時が、希薄だった。
お世話ごわす
え?
あ、いえ、お世話様です
ああ、どうもこちらこそ
ええ、よろしくどうぞ
そうしてまた、短くなった、先のまるい鉛筆をつかって、彼女はたんねんに、じゅうたんの模様を見つめ、その模様を紙に描いている。
あら、また天気が変る。スコール、スコーレ。とてとてと、波間を犬が駆ける。あや、霧。あははは。