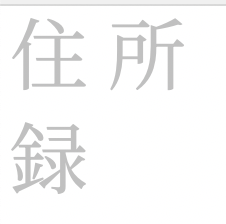あなたは仕事柄、よく散歩をしている。別に、歩く仕事をしている、というわけじゃない。
歩いていると、空洞の多い頭の中で、何かコロコロと転がる音がしている。言葉だろうか。
後ろの方から、何か人の気配がしている。呼吸するような声。はぁはぁといいながら、ジョギングをしている。蛍光色のシャツを着ている。蛍光がチラつくことで脳の回転に磨きがかかり、その揺れる速度をより速くしているらしい。右腕にはスマートフォンをくくりつけていて、そこから何か音が流れている。必死な感じのシティポップ。後ろから来ていたのが、ゆったりと歩くあなたを追い越し、その先へいく。この人は一体、何をしたいのだろうか。
と思うと向こうのほうから、スケートボードを必死にこいで走ってくる人がいる。リュックを背負って、ガッ、ガッ、ガッ、とこいでダーと走る。それを繰り返す。片手にはスマートフォンを握っている。その人もあなたのことを通り過ぎて、今度は後ろの方へ行き過ぎる。それが移動手段なのだろうけど、ずいぶんと大変そうだ。歩いた方がいいんじゃないだろうか。
「DIVE, DIVE, DIVE」
とびこめ、もぐれ、あたまからいけ。そんなことだろうか。向こう側の道の壁に、急に書いてある。コンクリートに鮮やかなスプレーの一筆がきで、これは路からのサインなのだろうか。そうして歩いていると、その言葉が歩き方にそって頭の中で、リズミカルに弾ける。あなたが好きなグミみたいな感じ。
あなたはそうやって、言葉や思考を待っているフシがある。九割くらいは、ささいな思いつきだったり、新しい冗談のアイデア、よく思い出す思い出、たずさわる職務の悩みだったりする。でも時おりしれっと、原石のような何かが転がってくる。そこから断章が生まれて、話がぽつりぽつりと、転がっていく。それ以外のあり方もあるのだろうけれど、あなたには今は分からないし、つかめない。
車道を川と考えるとその対岸に、あなたと同じ道筋を歩いている二人連れが、目に入る。一定の距離をおいたまま、前方の男性のような人は歩いていて、後方の女性のような小柄な人は自転車をひいている。おたがいに缶の飲み物をすすりながら、ぽつりぽつりと会話をしている。眺めていると、
「ねえ、どうやっていくの」
「そこの角で、左に曲がってあとはそのまま」
「そのままどうするの」
「歩くんだよ」
「もう疲れた」
「でも、歩くんだよ……」
そう言いながら、そこの角を左に入っていく。距離を置いているけれど、手を二人つないで、前の人が後ろの人の手を引いていくみたいな雰囲気も感じられる。それもまた歩きのかたちなんだろう。あなたはゆっくり、そのリズムを保つように考えながら歩いているから、まだそんなに疲れていない。
その角の左の方には、あなたがたまに訪れる飲み屋などが数軒、並んでいる。その店を横目に見ながら、二人は帰っていくみたい。それか、一軒寄っていくんだろうか。
あなたは、ある時よく分からない村にいたことを、ふと思い出す。
その村は、幻想的な傾向のある村だ。暗闇の中に路地があって、その先に店の光がまたたいている。真夜中の、小さな飲み屋街の通りみたいだ。でもそうではなくて、ああした通りのつくりが、そのまま村になっている。山あいのその場所は、狭い平地をそうして細かく区切って、人たちが過ごしている。だからそこは昼の町でも、薄暗闇の路地が多く通っている。
そのようにあなたは回想をしていて、回想はしばらくつづく。
そこは風通しがいい場所だった。浮世離れした人が行き来している。というものの、そう思われているのはむしろ、あなたの方だった。観光をする人も少ないその地に、ふと訪れては勝手なことを言っている。どうして来たかというと、そこにもう一人浮世離れした知人が来ていたから。かれは当地での浮世離れを自覚しながら、その場所と空間を使って、店舗をしている。
店舗というのは、かれは、公共の空間や町の通り沿いに、新しい部屋をつくる。かれ、と言ってると馴染みがでないので、仮に、八子さんとしておく。八子さんがつくるそこでは、住民たちが物々交換をして、みんなの部屋をつくっていく。生身のインスタレーションみたいに住民が日々行き来して、仮想の居間が、実際の居間になっていく。しかし実は作品でもある。そんな説明でいいのかは、あなたには断言できない。
居抜きで改装された部屋は、三つの部屋に分れている。窓や壁などなく、縁側ごしに、断面図のように路上に開け放たれている。そういうと作品っぽくきこえるのだけど、その集落ではむしろ普通で、昼間は開け放って夜は布でおおいをする程度のつくりが主流だったから、違和感はなかった。
縁側は竹で編まれたテラス。部屋の内部はすべて水色のペンキで塗られ、三部屋を分ける壁は白かった。動き続ける舞台装置のよう。しかしそこは舞台ではなく、生活の一場面で、そうしたあわいに店舗がゆれている。
「住民が、何やってるんだろう。たかってやれ。って集まってくるよね。僕はそれに乗ったらあっちのペースにのまれるな、と思って、無視していた。それで淡々としていたら、こっちのルールに乗ってくれるようになった」
あなたが行った頃には、もうだいぶ部屋は部屋の体をなしていた。はじめは、八子さんが用意した、古びた赤いカーペットしかなかったらしい。
部屋に入る。真ん中の大きな部屋で、人がそこに寝そべったりご飯を食べたりするメインルーム。壁には、物々交換したものを描いたワッペンがある。こう布にひとつひとつ書いていき、壁に貼った地図上の、交換してきた場所にピンで留めていく。ここでこの日に、イスとぬいぐるみを交換した。この家を訪ねて、トナカイの置物をもらった。壊れたイスをもらった。イヌが着いてきて気づいたら居ついている。それがこの店の日課だ。店というか、装置というか。八子さんは装置をまわす素材として、そんな日課を設計していた。日課は時間を生む。住民たちはそれにつきあって、一日のうちの、ある時間を過ごしていく。ひまな子たちは沢山、遊びに過ごしている。
日課は、他にもある。朝晩、店舗を開け閉めすること。八子さんや手伝いのスタッフが日記を書くこと。それと毎週欠かさずその週の出来事を編集した「手紙」をつくって、支援者たちに送ること。
向って右側の部屋。壁には壊れた傘や、子供用の民族衣装のようなもの、落書きが沢山貼ってある。たむろする子どもたちが描いたのだろう。床には円いイスのようなもの。それでもう一つ壊れかけた藤椅子があって、子どもが座ったり転がしたりして遊んでいる。あなたが滞在している間ちょうど、この部屋に大きなソファが入った。民家から皆で運んだ。八子さんともう一人の男性が前後で背負って、その周りを子たちが囲んで賑やかにしていた。
日々、物々交換がされて、だんだんと居間のかたちが出来てくる。時間はゆるやかで心地いい。12時から18時の開店の間、人びとはかわるがわる訪れて、テラスに座ったり、何かいじったり、手仕事をしたり、世間話をしたりしている。子どもは遊びほうけ、時に小さな子が泣きわめく。店の前では車や人、鶏や鴨や犬などが行き来している。そうしていると村の生活に馴染んでしまうのが面白くないから、ときに料理をする。流しそうめんをする。仮装して、町を練り歩いたり、祭りのような事をする。それは町の暮らしと境界線がとけていって、お店が生活のなかにとりこまれるのを、押し留めようとしているという。
そう、雑な音楽や、男女の嬌声などが遠くに聞こえている。それはあなたにとっては懐かしい、何だかピュアな骸骨みたいなものがうろうろ動いている様。それがどうして懐かしいのか、なにか昔にみていたのだったかは分からないけれど、どこか見覚えがあった。骸骨のようなものをかぶって、人たちは踊ったり、町を練り歩いたりしていた。それについて歩いていくと、火を焚いている小さな家に、女性が出迎えをしていて、ポップな仮装はその入り口で何かやりとりを行なう。それで気づくことには、彼らの見積もりでは、それは平坦な時間を揺さぶるハレの催しだったけど、この地には既にあった。既に日常に祈りがあった。自分たちであわいへ向かう、パラレルワールドがあった。
それで、あなたは歩いていると、遠くに何か飲み屋の喧騒がしている。いつしか、そこにある石でできたベンチに腰掛けている。いつも、ふと座りたくなるベンチだから、座って、そこのコンビニエンスストアで買った缶のサワーを飲んでいる。乾いた風が心地いい。季節はもうあれだな、秋なんだな。いや、秋も終わるのか?
その部屋があった国も、秋だったのか? 乾いた風が吹いていた。熱帯だけれど山あいだったから、そう暑くなくて、時折霧のような雨がふって、すぐに乾いていた。時々、強い乾いた風が吹いていた。どちらかというと涼しくて程よかった。
ああ、そうして思い出したように、部屋の左側の部屋を見る、大きなものはないが、何か作業をする。イモを焼いたり、ニンニクを干したり、何か書いたり、機械を触ったり。だから子どもは入りづらそうにしている。あと、棚のようなものに、不通のデンワや錆びて真黒になった地球儀、錆びた箱などが置いてある。あとは、カゴが少々。これは彼らが物々交換に繰り出す際に背負っていくカゴ。そこにある電話機で、いつも遊ぶ女の子が居た。「もしもし、もしもし」言うとスタッフのYさんが応答する。「もしもし?」まだ先の仮装のやりとりが、頭に戻ってくる。
過ごしていると、子どもがどんどん膝や手足に集ってくる。まとわりついたり、慌ただしい。あなたはぼけっとして、何を思ってそこにいるのだろうか。何も思っていないということはないのだろうけど、明確に何かを考えていたのか。そうして、ノートに何かを書きつけている、その場にいる実感とか景色の描写。あるいは今遠くにいった暮らしのこと? もうノートは残ってないけれど、そんなことだっただろう。残してきた暮らしでは、男女のつきあいをしている相手がいて、離れてみてその人に感じることがあったのだろう。そこにいると、時間や空間は、ありあまる程あるように思えたから、少し離れて考えることができた。
書く間、おじさんが、あなたの手元をずっと見つめている。彼は色黒で、浅い筒みたいな帽子を被っていて、瞳は灰に薄青、とても澄んでいるし、一部はとても充血している。何か、コトバを教えてくれた。ノートの左上に書いてもらっている。血管がとても立った骨太な手で、書かれ続けるままになっている。何て発語したのか全く覚えていないから記号にしてみると「●○●○●○」と確か言いながら書いていた。現地ではそう発音されるらしいがどうも「△▲△▲△▲△」としか耳に馴染まない。何故だろうか。言いやすさからか。気づくと手に何か缶をもって飲んでいて、あなたにそれをすすめてくる。とてもケミカルな香りの飲料で、これはあれだ、
「ストロングゼロ飲んでるの。だめだよそれは身体によくない」あなたは首をななめにふって手を上げて辞する旨を伝えたところ、おじさんは少し残念そうにそれを手元に戻す。もう片方の手には大きな、傘が手のひらほどもあるナメコのようなものをつまみに持っていて、それは少し食べたいと感じたが気後れしてそれは言えなかった。
さっき言った左の部屋では、現地に住まう通訳のRさんがおばさんと話し込んでいる。何を話しているかは勿論分からない。Rさんは先ほどまで、何か大きい記録帖のようなノートに、書き物をしていた。それが、日記のもとなんだろうか。部屋の片隅にはドアがあり、その中の物置、は唯一布で外界から隠されていて、通信するための電子機器などがはいっている。
左の部屋のもっと左端、ほぼ外みたいな部屋もあって、服が沢山置いてある。ここは一応交換をする商店だから、ここが一番店と言えば店っぽいが、持て余しているようだ。真ん中に足ふみミシンがあって、そこによく犬が寝そべっている。
利き目が右だからか、見ていると、視線はいつも、左へ、左へとすべっていく。すると、もっと左の部屋があって、そこまでいくともう、だいたい外だった。人たちはそこで借りてきた器具で食事をし、その地域特有のお茶をつくり、掃除をし、遊んだり、打ち合わせをしたりする。たまに、お婆さんが集まって、そこにある食器でお茶を囲んだりしている。子だけじゃなくて大きい人たちも、竹のテラスに寄りかかり、世間話をしている。
そうして1日に数回、この部屋の調度を集める物々交換のため、店員と子どもたちは町を練り歩く。子どもたち、時に大人や青年を交えて、「・・・、・・・」「・・・、・・」と節をつけて呼びかける。
セルフフィクション。そんな曖昧な感じで、あなたの記憶が戻ってくる。思い出す時って、時間がいる。自分の声を引き戻している。それは他人の声を思い出すのにも似ている。だいたい書くものも、おそらく、考えて話すということも、そこに実際に起きたこととは異なるし、ある種の嘘をはらんでいる。具象絵画というのが、絵具というものを使った抽象であるのと同じように。
あなたは時折そうやって、あてどもなく歩いていて、ときに座って、ただただそれを繰り返して。リズムの中で何かに気づいたり、見えてくる何かがあった。そういう時間があった。座って考えていると、急にしとしとと雨が降り始めるから、あの村みたいだなと思う。けれど村とちがって、ずいぶん湿り気のある雨だ。気持ちいいかもしれない。でももう帰ろうかと感じて、また歩き始める。しかし、そもそもどうして、あの八子さんの商店に行ったのだったか。かれと会ったのはとある川で、そのときも川で何かをしていて、少し言葉を交わしたくらいだった。あの作品、あのふるまいに惹かれたというのもそうだし、お休みに旅をしたかったというのも覚えている……、そんなことを考えながら、あなたはそのまま歩いて、いつか道を折れて、家路について、家の階段を上りドアを開ける。まだ夜がつづいていて、そこにも三つの部屋がある。右の部屋をちらりと見て、真ん中の部屋にすわる。左の方に視線をやるとそこは和室で、そろそろ冬も近いから、コタツがでている。
コタツの中には、わたしがいる。
わたしは本を読んでいるような、携帯電話をながめているような、ぼんやりしているような感じ。ただいま、と声をかけると「ああ」とうなずく。あなたは、わたしという人とどのように会話をしているのか、いつもどうやってコミュニケーションしているのか、不思議に思う。一番最初に交わした会話は何だったか。そこからすべては続いているはずなのに、どうも内容は曖昧だ。この部屋はずいぶん静かなもので、ときに二人は画面上の文字だけでやりとりをして、そのまま寝てしまう。どうしてここではあの町のように、人がたくさん行き来をしていないのか。
人と話すということとは、なんだろう。だいたい彼らは、どのように、何を話していたのか、それであなたは、何を話したのだったか、あまり記憶していない。言語が分からなかったから、内容がわからなかったから? でも、普段はなされている大体も、大抵は意味なんてないし、内容もない。言葉になる、ならない。それは人が、あとから決めたことなんだろう。そんなことの手前に、何かがあった。ただ彼らは、あなたに興味を抱いていて、何をそんなに考えているの、何をそんなに観察しているの、そんなことを考えてあなたの瞳を覗き込んでいるようだった。
「ねえ聞いて、詐欺にあったんやけど!」そんなことを急にいう。
人は記憶したことを全て脳に刻んでいるという。音や匂いなんていうのもそうで、全て蓄積されていて、何かの刺激でフラッシュバックしてくるみたいだ。その方が面白いっていうのに、どうして言葉に頼るのだろうか。これは記録をしていく道具や装置なのだろうか。
だからその中にわたしはいる。あるいは、わたしはいない。
そうしたあなたとわたしの部屋のちょうど向かいには、まるで鏡写しみたいに似た部屋が、アパートの外階段をはさんで、ある。同じ二階建てのアパートで、そこは、そこだけ独立して二階になっている。ドアを開けるとちょうど、正対している同じ高さくらいに同じくらいのドアがある。その部屋の二人もコタツに入っていて、昔の記憶や最近の出来事について、語っている。曰く、画面ごしの打合せが最近になって増えたから、自分の顔ばかり見るようになった。しかも動いている。そんなことはこれまでなかった。見ていると思い出される人の顔かたちがある。それは母だった、だから母に「こんにちは」と声をかけてみる。
そうしてまた、日をかえて、八子さんに会う日があった。